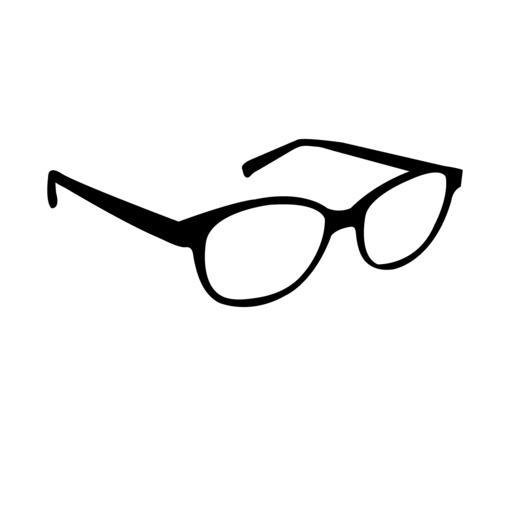こんにちは、メガネです。
・ビジネス実務法務2級の合格率は40%~50%
・合格率が高い理由は3つ
- 公式問題集からの出題が多い
- 試験範囲も広くはない
- マークシート式

ビジネス実務法務の合格率推移
まずはビジネス実務法務検定の3級と2級の2017年~2020年の合格率を見てみます。
※2020年はコロナ影響で1回分のみ。
2020年度の試験結果(12月の1回分)
| 級 | 実受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
| 2級 | 6,890 | 2,990 | 43.4% |
| 3級 | 9,372 | 7,097 | 75.7% |
2019年度の試験結果(6月、12月の2回分)
| 級 | 実受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
| 2級 | 12,552 | 5,140 | 40.9% |
| 3級 | 21,061 | 15,817 | 75.1% |
2018年度の試験結果(6月、12月の2回分)
| 級 | 実受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
| 2級 | 13,729 | 5,766 | 42.0% |
| 3級 | 19,808 | 15,711 | 79.3% |
2017年度の試験結果(6月、12月の2回分)
| 級 | 実受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
| 2級 | 15,504 | 6,125 | 39.5% |
| 3級 | 21,164 | 14,607 | 69.0% |
ここ数年は高い合格率が続いており、おおよそ2級は40~50%、3級は70~80%といったところです。
簿記3級の合格率がおよそ40%~50%程度ですので、合格率だけで判断すると比較的易しい試験であることが分かります。
実際、私も2級を取得しましたが上記合格率は納得できる難易度だったと感じました。
合格率にはばらつきがある
ビジネス実務法務検定2級のここ数年の合格率は上記の通りですが、合格率には回毎にばらつきがあります。
2017年で見ると年間を通しての合格率は39.5%となっていますが、6月の合格率が16.7%、12月の合格率が56.6%とかなり差があります。
とはいえ年2回の受験が可能ですので、しっかり学習した上で臨めば仮に1回目で運悪く難しい回にあたったとしても2回目の試験で合格が可能です。
ビジネス実務法務検定2級の難易度
次に、ビジネス実務法務検定2級の難易度についてです。
難易度は前提知識や職種によっても変わってきますので、まずは私の当時の状況について説明しておきます。
・職種:経理
・前提知識:なし(大学は工学部、法律系資格も保持していません。)
・学習方法:独学
つまり、法律に関しては完全に初心者の状態からスタートしたということです。
繰り返しになりますが、そんな私でもビジネス実務法務検定2級は比較的易しい試験だったと感じました。
そう感じた理由は大きく3つあります。
1.公式問題集から出題される問題が多い
これがもっとも大きな理由です。
公式問題集は、ビジネス実務法務検定を運営している東京商工会議所が出版している問題集になります。
問題集については、こちらの記事で詳細を記載していますので参考にしてください。

ネットで事前に調査した際にも、同様の所感は多く見られました。
これは法律知識のない私にとって、試験に対するハードルを下げる意味でかなり役立ちました。
暗記も多く単調になりがちな法律の学習が、この問題集を解いておけば確実に合格に近づくことがわかっていましたからね。
参考問題
参考までにですが、試験では下記のような問題が出題されます。
【問題】
A社は、Bに対して1,000万円の金銭債権を有しており、その弁済期は既に到来しているがBは弁済しようとしない。この場合に関する次の①~⑤のうち、その内容が最も適切なものを1つだけ選びなさい。【選択肢】
①Bは、その所有する唯一の資産である甲土地をCに時価で売却した。この場合、不動産を消費しやすい金銭に換えたとしても、時価による売却は詐害行為に当たらない為、A社はBが行った甲土地の売買契約について、裁判上、詐害行為取消権を行使することができない。②Bは、その所有する唯一の資産である甲土地をDに廉価で売却し登記を移した。その後Dは、甲土地を第三者であるEに譲渡し登記を移転した。この場合、A社は甲土地の所有権は転得者であるEに移転している以上、裁判で詐害行為取消権を行使することができない。
③Bは、Fに500万円を贈与したため無資力となった。この場合、A社が詐害行為取消権を行使するには、Fが詐害の事実を知っていたことを立証しなければならない。
④Bは、Gに500万円を贈与したため無資力となった。その後Bがその資力を回復し無資力で亡くなったときは、A社はBが行った贈与について裁判上、詐害行為取消権を行使することができない。
⑤Bは、Hに対し負担する買掛金債務の弁済に代えて、買掛金債務の額に比べはるかに効果な甲土地をHに引き渡し登記を移転した。この場合、代物弁済は詐害行為に当たらない為A社はBが行った代物弁済について裁判上、詐害行為取消権を行使することができない。
出典:ビジネス実務法務検定試験公式問題集2級
ちなみに正解は④です。
いかがでしたか。全く試験勉強をしていない現時点では何のことかさっぱり分からない方が多いと思います。
易しめの難易度とは言え、このレベルの問題が多く出題されますので公式問題集でしっかりと対策をした上で試験に臨むようにしましょう。
2.試験範囲は広くない
試験で問われるのは民法・商法が中心です。
民法に関しては本来条文が多く範囲が広いのですが、ビジネス実務ではその中でも一部のみが試験範囲となっています。
書店で並んでいるテキストを見ると分かりますが、テキストは一冊に収まる程度です。
多少分厚く感じますが、図解や例題、条文などが記載されていますのでサクサク次へ進みます。
また、試験範囲が広くないことに加え試験で問われやすい範囲も傾向があります。
出題されやすい範囲は別記事で紹介しているテキスト(翔泳社:完全合格テキスト)に記載されていますので、該当範囲を集中的に学習し効率よく学習を進めましょう。
3.記述式でなくマークシート式
ビジネス実務法務は2級まではマークシート式です。
その為、正確な知識がなくても消去法で正解を選べます。
とくに民法では、上述したように当然の結果と言える内容も多いため、マークシート式だとそういった問題で点数を稼げるのも合格率をお仕上げている理由のひとつです。
これら3つの要因が合格率を上げている理由です。
まとめ
ビジネス実務法務は就職・転職では限られた職種でしか効果を発揮しませんが、法律を体系的に学びたい方にはうってつけの資格です。
難易度が易しく、幅広くビジネス法務を体系的に学習できます。
また合格率が高いため、モチベーションを高く維持しやすい点もメリットの一つです。
ビジネスマンとして何か周りとは違った強みが欲しい、法律を体系的に学びたい、そんな方にはおすすめの資格ですので是非チャレンジしてみてください。
それでは!